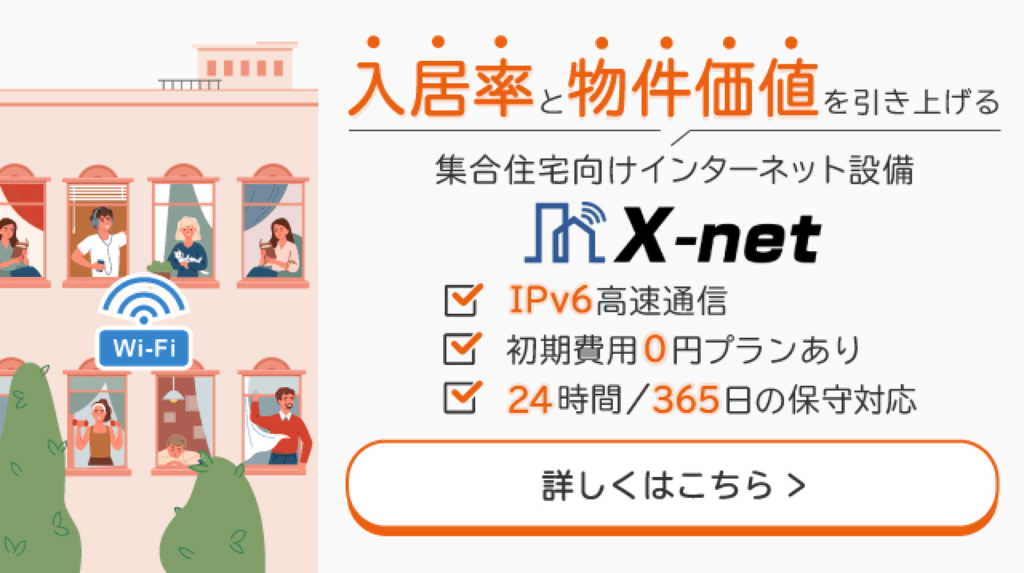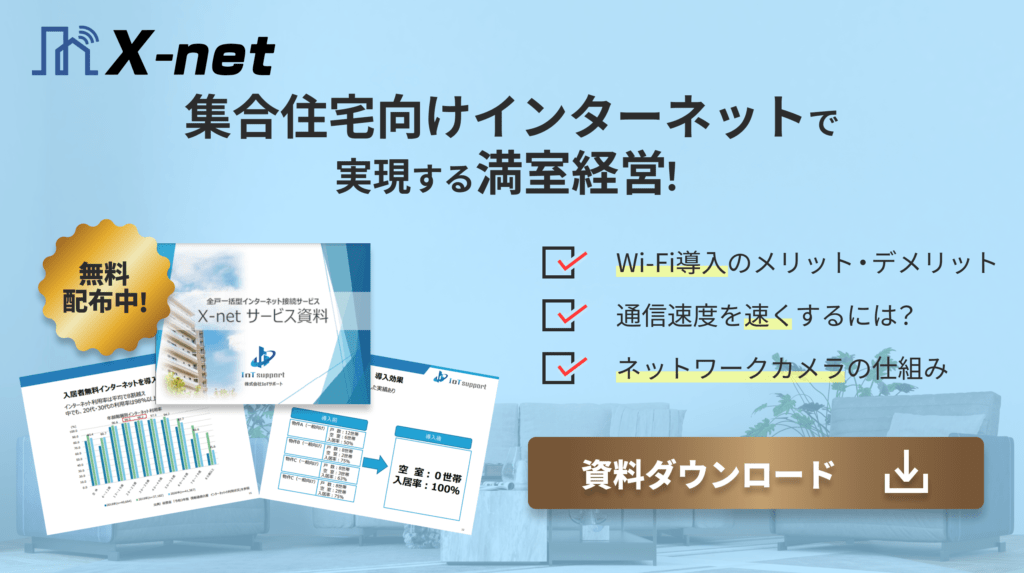不動産オーナーになるためには?不動産経営に必要なことや流れ・成功の秘訣を徹底解説!
2023年2月27日「安定した副収入を得たい」「資産運用をしたい」などの目的から、不動産オーナーに興味を持つ方が増えています。実際に不動産オーナーを副業にしている方は多く、安定した収益を得ている方もいるようです。
不動産オーナーになるために特別な資格は要らないので、資金の問題さえクリアすれば、すぐに始められます。資金に関しても、銀行で不動産投資用のローンを組めるので、一般的な会社員であっても準備できるでしょう。
その一方で、不動産オーナーとして失敗してしまうケースも珍しくありません。失敗しないためには、いきなり投資用物件を探すのではなく、必要なことや流れを知っておくことが大切です。
今回の記事では、不動産オーナーになって収益を得るために必要な知識や成功の秘訣について解説します。
不動産オーナーに興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
不動産オーナーとは?

「不動産オーナー」とは、マンションやアパートなどの不動産を所有し、それらを貸し出すことで利益を得る人のことです。不動産オーナーになるためには、特別な資格は必要ありません。
しかし、ある程度不動産に関する知識があったり、法律に詳しかったりする方が有利です。なぜなら、不動産オーナーになるためには様々な契約が必要だからです。
不動産や法律に関する知識があれば、よりスムーズに話が進むでしょう。
不動産オーナーになるために必要なこと

不動産オーナーになろうと考えたとき、対象となる物件の確保や自己資金の準備から始める方も珍しくありません。
しかし、そういった物件や資金以外にも、不動産オーナーになるために必要な準備があります。何の準備もせず、勢いだけで不動産投資を始めると、失敗するリスクが高まります。
そこで、不動産オーナーになるために必要なことについて解説します。
不動産投資の勉強
1つ目は、不動産投資の勉強です。
例えば、マンション経営を始める際は、その物件で収益を上げられるのか見極めた上で購入することになるでしょう。
収益が上がるか見極めるためには、物件のクオリティや間取り、そして周囲の家賃相場、環境、空き家リスクを含む調査が必要です。不動産投資の知識があれば、調査を正確かつスピーディーに行えます。
また、資金の借り入れやそれに伴う利息、不動産登記の手続きなどの勉強も大切です。不動産オーナーに資格が不要だからと言って、不動産投資の勉強を怠らないようにしましょう。
審査に向けた自己資金の準備
不動産投資を始める際は、金融機関で不動産投資用ローンを組めます。しかし、全額ローンを組むことはできないので、頭金として自己資金の準備が必要です。
不動産投資用ローンの場合、借り入れ金額の約1割程度が頭金と諸経費でかかると言われています。例えば、2,000万円の投資用マンションを購入する場合、最低でも200万円の自己資金が必要です。
ローンの審査を受ける際は、自己資金が必要なので物件探しをする前に準備しておきましょう。
不動産オーナー交流会への参加
都市部を中心に、不動産を所有しているオーナーや個人投資家向けに交流会が行われています。実際に不動産投資をしているオーナーや、自分と同じ志を持った人と交流を持てるため、大変参考になるでしょう。
また、不動産オーナーだけでなく、金融機関の融資担当者や弁護士、さらに税理士といった専門的な知識を持った人が参加することも多いです。そのため、実践的なアドバイスをもらうこともできます。
単なる情報収集だけでなく、人脈も広がるため、不動産投資を続けていくモチベーションにも繋がるかもしれません。
不動産オーナーになるまでの流れ

不動産オーナーになるまでの流れで最も重要なのが、信頼できるパートナーを見つけられるかどうかです。パートナーとしては、投資用物件を紹介してくれる不動産会社やハウスメーカーなどが挙げられます。
ここでは、不動産オーナーになるまでの流れについて詳しく解説します。
不動産会社に相談する
まずは、信頼できる不動産会社に相談しましょう。新築物件の場合は、加えてハウスメーカーが関わってくるケースもあります。
不動産会社やハウスメーカーは、不動産投資のプロです。不動産投資を始める際は、不動産会社やハウスメーカーから経営プランの提案を受けます。経営プランの提案では、立地条件や周囲の環境、人口動向など具体的な情報を得られます。
信頼できる業者を見つけるために、複数の不動産会社に相談を行い、比較検討するのもおすすめです。
金融機関のローン審査を受ける
購入する物件が決定したり、建築プランと大まかな見積もりを受け取ったりした後は、 金融機関に対してローン審査を申し込みます。マイホームの購入と同じく、不動産投資でも専用のローンを組むことができます。
購入時のコストだけでなく、ランニングコストもしっかり把握した上で資金計画を立て、無理のない借入額で審査を申し込むことが大切です。不動産投資用ローンも住宅ローンと同様に、仮審査と本審査があります。それぞれ必要な書類が異なるので、注意が必要です。
不動産の請負契約を締結し決済・引き渡しを行う
無事にローンの本審査に通ると、請負契約の締結や決済、建物の引き渡しをします。新築する際は、不動産会社と建築工事の請負契約を締結します。
建築請負契約には工事の報酬や内容が詳細に記されているので、十分なチェックが必要です。後々トラブルにならないようにしましょう。
新築の場合、契約時、着工時、引き渡し時ごとに分けて支払うのが一般的です。
どのタイミングでどれくらいの金額を支払う必要があるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
不動産オーナーになるメリット

不動産オーナーになることで、安定した収入源を作れるだけでなく、税金や保険の面でも様々なメリットを得ることができます。
ここでは、不動産オーナーになるメリットを紹介します。
- 長期的に安定した収入源を作れる
- 税金対策になる
- ローンにより少ない元手で始められる
- 私的年金・生命保険の代わりになる
長期的に安定した収入源を作れる
不動産オーナーになることで、長期的に安定した収入源を作れます。不動産投資は、管理の手間がかかりますが、不労所得を得られます。
管理業務も外部に委託することで、サラリーマンとして企業で勤務しながら、副収入を得ることができます。万が一病気や事故などで自分が働けなくなっても、生活を支える安定した収入源があれば安心できるのではないでしょうか。
また、他の投資としては株式や暗号資産、FXなどが挙げられます。それらと比べると不動産は価格変動が非常に緩やかです。
他の投資とは異なり、一晩で価値が暴落するようなことはありません。不動産投資は、比較的低リスクの投資であると言えるでしょう。
税金対策になる
現金が手元にある場合、不動産に変えておくことで、相続税や贈与税を節約できる可能性があります。不動産には独自の財産評価方法があり、購入時の価格より評価が下がったときには、相続や贈与において生じる各種税金も低くなります。
また、所得税や住民税などの税金対策も可能です。不動産投資によって得た利益は、所得税や住民税の課税対象です。
しかし、不動産経営には必要経費が多く、赤字になった際は、確定申告をすれば納税した所得税から還付を受けられます。
不動産投資では、建物や設備などにかかる費用を数年に渡って費用として計上する「減価償却」が可能です。
これによって、実際の手元に残る金額より低い所得で申告できます。ただし、いずれも行き過ぎた節税対策は脱税と見なされる可能性があるため、正しく理解した上で行うようにしましょう。
ローンにより少ない元手で始められる
不動産オーナーになる際には、銀行から資金を借り入れる必要があります。ローンを活用することで、少ない自己資金で不動産オーナーになれます。
また、ローンは家賃収入から返済するため、基本的に自己資金は減りません。ローンにより少ない元手で始められるというのも、メリットの1つです。
私的年金・生命保険の代わりになる
銀行から融資を受けてローンを組む場合、団体信用生命保険に加入しなくてはいけません。団体信用生命保険とは、万が一契約者が死亡した際に、残債を保険金で支払うことができる制度です。
ローン返済中に亡くなったとしても、不動産はそのまま残るため、家族にとっての生命保険代わりになります。さらに、定年までにローンの支払いが終わったのであれば、家賃収入を生活費に充てることができ、私的年金の代わりにもなります。
不動産オーナーになるデメリット

比較的低リスクかつ資産形成をしながら収入を得られる不動産オーナーにも、デメリットはあります。
ここでは、不動産オーナーになるデメリットについて解説します。
- 不動産は流動性が低い
- 維持コストがかかる
- 管理・維持に手間がかかる
不動産は流動性が低い
株式のような金融資産の場合、比較的すぐに売却できます。しかし、不動産はすぐに売却できるとは限りません。
不動産を売却する際は、仲介業者に依頼をして買主を探してもらう必要があります。売却までの期間は、物件の立地や市場などの条件によってさまざまです。
希望額で売却できないこともあり、そもそも売却できるかどうかも確かではありません。不動産は高額であるため、流動性の低さに注意が必要です。
維持コストがかかる
不動産投資をする上で忘れてはいけないのが、維持に必要なコストです。不動産経営では、固定資産税や火災地震保険料、修繕費など、さまざまな維持コストがかかります。
不動産としての資産価値を維持するためには、維持コストが必須です。築年数が経った際には、美装修繕などの空室対策を行う必要があります。
不動産オーナーになる際に、このようなランニングコストの見込みが甘いと、ローン返済に余裕がなくなってしまいます。
管理・維持に手間がかかる
不動産は、金融資産とは異なり「現物資産」です。そのため、不動産を所持している限り、維持や管理に手間がかかります。
賃貸経営を行うためには、修繕や清掃のような管理業務が必要です。また、家賃の入金滞納などのトラブルが発生した際は、入居者と交渉する必要があります。
しかし、そのような維持・管理業務は、管理会社に委託することもできます。委託することで維持・管理の手間を省けますが、管理費の支払いが必要です。
自分に合った方法で維持・管理を行いましょう。
不動産オーナーの仕事内容

不動産オーナーの仕事内容は、多岐に渡ります。
ここでは、不動産オーナーの仕事内容を紹介します。不動産オーナーの仕事内容は、主に以下の4つです。
- 入居者の募集
- 家賃の集金・催促
- トラブルや問い合わせの対応
- 解約業務・退去の立ち合い
入居者の募集
不動産オーナーになって最初に行うのが入居者の募集です。一般的なのは、不動産仲介会社に仲介を依頼して入居者を募集する方法です。
賃貸物件の場合、賃料1ヶ月分の仲介手数料を不動産仲介会社へ支払うことで、入居者の募集から交渉、そして実際の入居に伴う契約手続きなどを任せられます。
家賃の集金・催促
不動産オーナーは、毎月入居者から家賃の集金を行います。少し前まではオーナーに直接手渡しするような物件もありましたが、現在では銀行振込による集金が一般的です。そのため、それほど手間はかかりません。
入居者には「どの銀行口座に何日までに入金するのか」を伝えておきましょう。しかし、入居者によっては、支払いを忘れてしまったり、数ヶ月滞納したりするトラブルが起きます。
家賃滞納や未納がある際は、書面または電話での支払い催促が必要です。
トラブルや問い合わせの対応
不動産物件を自分で管理するのであれば、トラブルや問い合わせの対応を自分でする必要があります。例えば、物件内でトイレの故障や雨漏りが起きた際は、すぐに駆けつけて業者を手配します。
建物に関しては、建築会社や工務店に発注することですぐに解決できるでしょう。ただし、隣人トラブルも不動産オーナーが対応しなくてはいけません。
入居者同士のトラブルは突発的に発生するケースが多く、速やかに対応する必要があります。
解約業務・退去の立ち合い
入居者が退去する際は、立会いが必要です。立会いでは、汚れや消耗、破損の原状回復費用について話し合いをします。
基本的に住居用の物件であれば、原状回復工事は不動産オーナーが手配し、入居者の負担分は敷金から差し引くのが一般的です。
しかし、原状回復費用を巡るトラブルが起こるケースも少なくありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に話し合う必要があります。
不動産オーナーの業務を委託できる管理会社とは?

ここまで、不動産オーナーの仕事内容について解説しました。
管理会社とは、不動産オーナーの業務を代行する業者のことです。不動産オーナーは、管理委託費を支払うことで、業務を管理会社に委託できます。そのため、他に本業があっても賃貸経営をすることができます。
不動産オーナー自身が物件を全て管理しているケースは珍しく、業務の全てもしくは一部を委託するのが一般的です。管理会社に支払う管理委託費は、家賃の5%程度が相場です。
不動産管理会社との契約形態は2種類ある
不動産管理会社との契約形態は、以下の2種類です。
- 部分的な管理を委託する集金代行契約
- 物件管理を丸ごと委託するサブリース契約
それぞれ委託できる内容と手数料が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
部分的な管理を委託する集金代行契約
部分的な管理を委託するのが「集金代行契約」です。集金代行契約という名称の通り、家賃の回収や送金といったお金周りの業務を管理会社が代行してくれます。
家賃の支払いは毎月必ず発生します。毎月発生する業務を外部に委託することで、維持管理にかかる手間を省くことができるでしょう。
| 集金代行契約のメリット | ・毎月発生する煩わしい業務が減る
・あくまで委託するのは一部業務のため、手数料を抑えることが可能 |
| 集金代行契約のデメリット | ・依頼できるのはあくまで集金業務のみであり、入居者の募集や建物の管理は自分で行う必要がある
・自分で入居者の募集を行うことで、空室リスクが高まる |
このように一部の業務だけを委託するため、オーナーに入る家賃収入はあまり減りません。一方で他の業務は自分で行う必要があり、手間がかかるでしょう。
特に物件の空室リスクについては、慎重に検討しなくてはいけません。空室は所有しているだけで、維持費がかかります。
1部屋あたりの家賃収入は高くても、空室が増えると赤字になってしまうかもしれません。
物件管理を丸ごと委託するサブリース契約
「サブリース契約」では、物件の管理を丸ごと委託します。管理会社が賃貸物件の経営を代行するため、不動産オーナーとしての仕事はごく最低限になるでしょう。
サブリース契約を結ぶ企業に対して、オーナーの物件を丸ごと貸し出すと考えるとイメージしやすいかもしれません。
| サブリース契約のメリット | ・賃貸物件を経営するにあたっての業務を全て委託できる
・空室があっても管理会社から補償を得られる |
| サブリース契約のデメリット | ・集金代行契約よりも管理委託費が高いため家賃収入が低くなる
・契約更新時には最低限支払われる賃料が下がる |
本業が別にあり、副業として不動産オーナーをしたいと考えている方は、サブリース契約がおすすめです。また、空室があっても、家賃収入がゼロになることはありません。
その一方で、管理委託費が集金代行契約よりも高いため、手元に入る家賃収入は減ります。
不動産オーナーが物件選びで気を付けたいポイント

賃貸アパートやマンションは、探している人にとって魅力的でないと入居に繋がりません。不動産オーナーになる際は、物件選びを慎重に行う必要があります。
ここでは、不動産オーナーが物件選びで気をつけたいポイントについて解説します。
物件のニーズ
物件を選ぶ上で特に重要なのが、物件のニーズです。物件としては魅力的でも、不便な場所にあると入居希望者が現れづらいので、立地はとても大切です。
不動産オーナーとして収益を上げたいのであれば、賃貸需要の高い場所に不動産を取得する必要があります。交通の便に優れている場所や、日当たりが良く駅に近い場所など、立地条件の良い物件は、ニーズが高いと言えるでしょう。
物件の将来性
今現在の人気だけでなく、物件の将来性にも目を向けてみましょう。物件周辺に都市開発の予定があるかなど、物件の将来性も大切です。
例えば、将来病院や大学といった施設ができるのであれば、そこで働く職員や学生の賃貸需要が高まることが予想されます。
また、近隣に大規模なショッピングモールの建設が予定されているのなら、利便性の上昇から、周辺エリアの家賃相場が上がることが考えられます。
物件を選ぶ際は現状だけでなく、物件の将来性もチェックしておきましょう。
購入するタイミング
不動産オーナーになるならば、購入する物件の価値を慎重に見極めたいと考えるでしょう。しかし、立地に優れており、交通の便が良い人気エリアにある物件はすぐに買い手がついてしまいます。
迷っていると他のオーナーに購入され、タイミングを逃してしまいます。優良な物件を見つけた際は、購入するタイミングを逃さないための決断力が必要です。
また、常に狙っているエリアの情報を得て、いつでも購入に踏み出せる準備をしておくことも大切です。
不動産オーナーとして成功するためには?

不動産オーナーは特別な資格を必要とせず、資金もローンを使用できるため、興味を持つ方が多い投資方法です。しかし、全員が不動産オーナーとして成功するわけではありません。
では、成功する人はどのような点に注意しているのでしょうか。
物件選びの際は現地に足を運ぶ
良い条件の物件は当然人気が高く、すぐに買い手がついてしまいます。タイミングを逃さないためにも、売り出されたらすぐに購入する方もいるようです。
しかし、賃貸物件を経営するにあたって、入居者がいなければ収入に繋がりません。現地に足を運んで実際に物件を見て、自分だけでなく入居者から見ても魅力的であるかどうかを確認しましょう。
入居者目線の経営をする
賃貸物件の経営は、入居者を優先的に考えられる人が向いています。入居者がいるからこそ自分の収入に繋がると考え、長く住んでもらえるように工夫をしたり、より良い環境を作ったりといった経営が大切です。
入居してもらったら終わりではありません。不満を持つ入居者がいれば、親身に聞き取りを行い、解決することがオーナーには求められます。
リスクもあることを理解する
不動産オーナーにはリスクもあります。賃貸物件の経営で代表的なリスクは空室です。空室が発生すると、その分家賃収入が減ってしまいます。
また、空室リスクの他にも、隣人トラブルや災害リスク、家賃滞納など、賃貸経営には様々なリスクが付き物です。そのようなリスクがあることを理解し、あらかじめ対処法などを考えておく必要があります。
不動産オーナーとして失敗しやすい人の特徴

不動産オーナーになったは良いものの、思うように収益を上げられず、失敗してしまう方もいます。
失敗してしまう原因は人それぞれですが、共通しているのは以下の2つです。
- 利回りの高さにこだわる
- 不動産オーナーになって満足する
利回りの高さにこだわる
不動産オーナーに限らず投資をする際、表面利回りばかり気にする方が多いようです。不動産投資にあたって表面利回りが高い物件というのは築年数が古く、利便性が低いエリアにある場合が多いでしょう。
このような物件は当然購入価格が安いものの、入居者側からすると古い上に不便な場所にあるため、魅力的だとは言えません。表面利回りばかりを重視し、入居者の立場に立って考えられないオーナーは、失敗する可能性が高いでしょう。
不動産オーナーになって満足する
不動産オーナーになろうと考え、実際に物件を購入した時点で満足してしまうような方も失敗しやすいです。不動産オーナーになって満足し何もしなければ、思うような収益は上げられません。
入居者を維持するための努力ができなければ、賃貸経営を続けるのは難しいでしょう。また、賃貸を経営していく中で、想定外のリスクが発生するかもしれません。
不動産オーナーになって満足してしまうと、想定外のリスクに対応できません。そのようなリスクに備えて、準備や対策をしっかりと行うことが大切です。
不動産オーナーになった際の注意点

実際に不動産を購入してオーナーになったとしても、そこで終了ではありません。不動産オーナーになってからも不動産に関する勉強を続けたり、リスクに備えたりする必要があります。
ここでは、不動産オーナーになった際の注意点について解説します。
情報が正しいか判別するようにする
不動産オーナーは、情報を収集しながら経営を行う必要があります。入居者維持の施策を実施したり、新たに物件を取得して収益拡大を狙ったりする際は、情報収集や勉強が必要です。
書籍やインターネットを使えば、どこでも簡単に不動産経営に関する情報を得ることができます。しかし、それら全てが正しいとは限りません。偏った内容が含まれているケースも珍しくありません。
また、不動産会社や管理会社の人は、自分たちの利益になる話を積極的にします。得た情報が本当に正しいのか、様々な視点から判断することが大切です。
失敗したときの対策を事前にしておく
不動産オーナーになったのであれば、失敗したときのリスクについても考えておかなければいけません。特に収益に直結するのが、空室の発生です。
空室が発生するとその間家賃収入が入らない上に、維持費用も発生します。賃貸物件を探しているユーザーには様々なニーズがあり、購入当初に想定していたニーズと合致しないケースもあります。
一棟だけでなく複数の賃貸物件を所有するなど、失敗したときのリスク対策をしておきましょう。
まとめ

本記事では、不動産経営に必要なことや不動産オーナーになるための流れ、成功の秘訣について解説しました。
不動産オーナーには必要な資格がなく、銀行の融資を利用すれば誰でも始められる投資です。比較的低リスクかつ資産形成をしながら利益を得られることから、近年注目が集まっています。
不動産オーナーには様々なメリットがある一方、デメリットやリスクも存在します。不動産オーナーとして成功するために、デメリットやリスクについてもきちんと把握しておきましょう。
不動産オーナーとして成功したい方や不動産オーナーになりたい方は、本記事を参考にしてみてください。