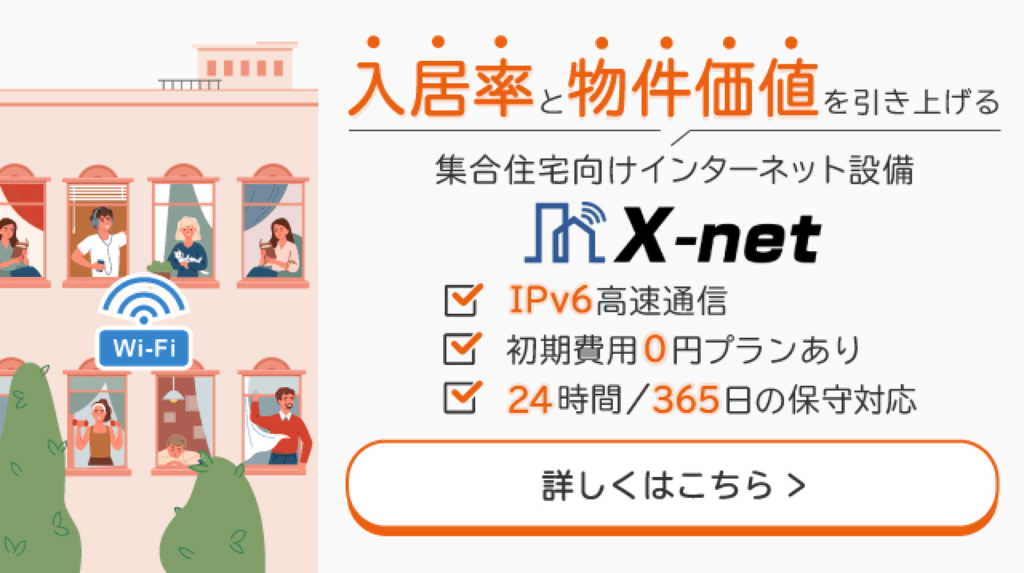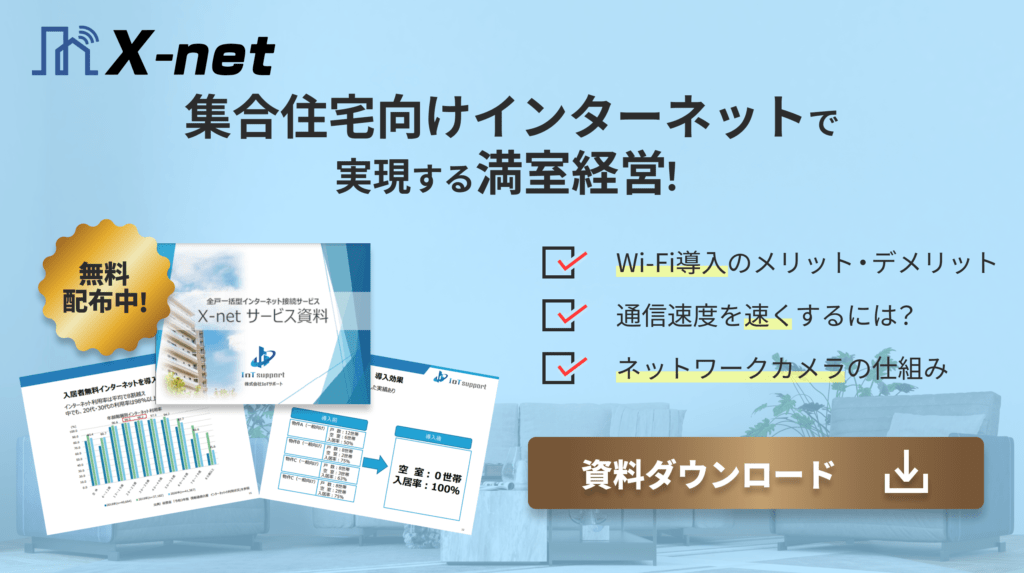5棟10室基準とは?基準を満たすとどうなるのかを徹底解説!
2023年2月21日5棟10室基準は不動産投資家が最初に目指すべき指標とされています。具体的にどういう意味で、基準を満たすとどうなるのでしょうか。
アパート1室から始めることの多い不動産投資は、1室の段階では業務規模とされますが、所有物件を増やしてある基準に到達すると、「事業と言える規模」になります。
どこからかお達しがくるわけではなく、「事業である」と自己申告することができる基準、それが5棟10室です。
この記事では、5棟10室基準がどのようなものか、達成することで得られるメリットや、注意すべきデメリット、達成した場合に必要な手続きなどを詳しく解説します。
不動産投資をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
5棟10室とは?

5棟10室は、事業的規模になる基準とされている指標です。不動産投資はアパート1室などからはじめるケースが多いですが、アパート1室は業務的規模です。戸建てなら5棟、アパートもしくはマンションであれば10室の不動産を所有すると、業務的規模から事業的規模に変わります。
事業的規模は税法上には記載がなく、社会通念によって行うとされているので、「おおむね5棟10室であれば実質的に事業的規模」であると判断します。
駐車場については、5台でマンション・アパート1室に換算されます。よって、駐車場50台の不動産を所有していれば、事業的規模であると判定されるのです。
5棟10室基準を満たすと認められる「事業規模」とは?

事業規模は、その仕事が事業主の生業(生計を立てるための仕事)となっているかどうかで判断されます。不動産所得は生業となっているかの判断が難しいため、5棟10室を形式上の基準としているのです。
しかし、基準に満たなくとも事業的規模と言えるケースもあります。例えば、所有しているマンションの賃料が高額で、年間を通して生計に足りうる十分な貸付け収入があれば、事業的規模と言えます。 所有する物件数が満たない場合でも、税務署に相談してみると良いでしょう。
事業的規模になるメリットは?

5棟10室になると事業的規模となるとわかりましたが、それでは、事業的規模になることで、どんなメリットが得られるのでしょうか。所得税控除におけるメリットが多いです。
- 青色申告特別控除を使える
- 事業専従者控除を使える
- 家賃回収ができない場合の貸倒損失を使える
- 資産損失分を経費に組み込める
それでは、1つずつ解説していきます。
青色申告特別控除を使える
青色申告特別控除は、事業的規模となることで最大65万円、業務的規模で10万円の所得控除が受けられる制度です。不動産所得から、必要経費だけでなく特別控除65万円を差し引くことができ、課税される所得額が低くなるので節税効果があります。
青色申告特別控除を65万円適用するためには、以下を満たす必要があります。
1)複式帳簿で、発生主義(取引された時点)で記帳する
2)青色申告時に、決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
3)e-Taxで申請、または電子帳簿保存する
1)、2)を満たすことで55万円の控除が受けられますが、最大額(65万円)の控除を受けるためには3)のe-Taxで申請しなくてはなりません。帳簿付けなど、手間がかかる作業ではありますが、業務的規模の控除額が10万円であることを考えると、65万円の控除は節税としてのメリットが大きいです。
事業専従者控除を使える
専従者控除とは、個人事業主の家族が事業に携わっている場合、その報酬を必要経費として控除できる制度です。控除の適用には、以下の条件を満たす必要があります。
1)事業専従者は、12月末時点で15歳以上の事業主と生計を一にする配偶者・親族であること
2)年間6ヶ月以上事業に専従していること
3)給与額等を事前に届け出ており、給与が実際に支払われていること
4)給与が労働の対価として見合っていること
専従者控除の適用には、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。また、給与については、資格を有している従業員より無資格の家族が高給であった場合、見合っていないと判断され控除されないケースもあります。
給与は年間数百万円になることもあり、専従者控除として差し引くことで課税対象となる所得が大きく圧縮でき、節税に繋がります。
家賃回収ができない場合の貸倒損失を使える
事業的規模になれば、家賃滞納による損失を申告できます。不動産投資における損失の多くは、家賃の滞納により起こります。
5棟10室未満の業務的規模の場合、回収できない家賃も収入として計上し、確定申告をしなければなりません。未回収が確定することで税金の還付を受けられるとしても、一旦は納税することになります。
一方、事業的規模になれば、滞納額は損失として申告できるようになります。不動産投資を続けていくためにも、手元の現金は減らさないほうが望ましいので、未回収分の納税をせずに済むにこしたことはないでしょう。
資産損失分を経費に組み込める
事業的規模と認められると、建物の取り壊しなどで生じた資産損失分を数年にわたり必要経費に組み込むことができます。
業務的規模では、その年のみ損害を必要経費として算入しますが、赤字にはできないので控除できる額は不動産所得が上限になります。
事業的規模になれば、損失額を全額計上することができ、所得額が赤字になる分も3年間は繰り返し損失額を控除することができます。
事業的規模になるデメリットは?

事業的規模になることは多くのメリットがありますが、デメリットもあります。デメリットは主に、事業の規模が大きくなることで、収入や管理物件が増えることに起因します。
- 所得税と住民税が高くなる可能性がある
- 個人事業税の対象になる可能性がある
- 副業規定に反する可能性がある
- 物件数が増加し管理が大変になる
それでは、1つずつ解説します。
所得税と住民税が高くなる可能性がある
事業的規模になると、所得税(国税)と住民税(都道府県民税と市区町村税)が高くなる可能性があります。所有している不動産が増えていくことで所得も増えるので、必然的に税負担も多くなっていくのです。
所得税は「超過累進税率方式」がとられているため、所得が増えることにより税率が高くなります。たとえば、所得が695〜900万円では23%の税率が、900万円を超えることで33%となります。
節税のメリットがある反面、増税の可能性もあるということです。
個人事業税の対象になる可能性がある
事業的規模になると、個人事業税の対象になる場合があります。個人事業税は各都道府県が課税する地方税で、青色申告特別控除を受ける前の所得から事業主控除の290万円を引いた額の5%に対して課税されます。
個人事業税は、課税対象となる不動産投資の規模も各都道府県が定めているため、事業的規模になっても、個人事業税の対象にならないこともあるのです。細かい条件は各都道府県に確認する必要があるので注意しましょう。
副業規定に反する可能性がある
不動産投資を副業として行っている場合、事業的規模になることで副業規定に反し、服務規定違反となる可能性があります。
不動産投資が副業として定着する一方、公務員などは原則副業は禁止されています。事業的規模はその業務が生業となるかどうかで判断しますが、事業的規模と認められるということは、副業の範囲を逸脱したとも言えるのです。
懲戒などの事例もあります。本人が経営に関わらないこと、運営を管理会社などに委託するなどの対応をした上で、勤め先に許可を得ることも検討しましょう。
物件数が増加し管理が大変になる
業務的規模になり物件数が増加すると、物件管理、税金管理といった物件を運営・維持するための業務も増えてきます。税金の支払いや手続き業務、ローンの管理、金融機関とのやりとりなどは基本的に事業主が行うため、入居者の募集対応、修繕、掃除といった物件管理は管理会社に業務委託するのが良いでしょう。
増えるばかりの作業を抱え込んでいては、次に所有する不動産の選定など、拡大につながる業務が行えません。
5棟10室基準まで規模を拡大するには?

5棟10室基準になることのメリットやデメリットを解説してきましたが、どのように事業を拡大していけば良いのでしょうか。
不動産投資の規模を拡大するには、以下のいずれかを行います。
- 物件を追加購入する
- より価値のある物件に買い替える
物件の追加購入は、ローンを完済しながら1つずつ物件を増やしていく方法です。
ロングスパンでの運用になりますが、物件が増えると一気に家賃収入が増えるメリットがあります。デメリットは、買い急ぐことでローンが重なり資金を圧迫することです。
買い替えは、所有物件の価値があがったタイミングで売却し、売却益などを利用してさらに価値のある物件に買い替える方法です。売却するため一時的に手元資金は潤沢になりますが、売却価値の低下により買い替えがスムーズにいかない場合もあります。
不動産投資の規模を拡大する上で最も注意しなくてはならないのは「借入過多」です。扱う金額が大きいため、空室で賃料が入らない場合など、一気に傾いて自己破産に陥るリスクも少なくありません。
早く目標に辿り着きたい気持ちを抑え、時間をかけて行うことが重要です。
5棟10室経営者が確定申告で必要な手続き

5棟10室の経営者になった場合、確定申告でどのような手続きが必要か確認していきましょう。
所有する不動産が事業的規模になった場合、不動産所得の確定申告を青色申告で行うことになるため、その年の3月15日(2023年分の確定申告から青色申告する場合、2023年3月15日)までに、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
また、専従者控除の対象になる従業員(家族)がいる場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も行います。
青色申告特別控除を適用するために、「発生主義の複式簿記で記帳」の上、確定申告書に加え決算書(貸借対照表と損益計算書)をe-Taxで申請、または電子帳簿保存します。所有する不動産が事業的規模になっても、所定の手続きを踏まねば節税効果のある特典などを受けることはできません。
面倒でも、必ず事前の届出や必要書類の準備を行い、節税のメリットを享受しましょう。
まとめ

5棟10室とは、業務的規模として青色申告ができる基準であり、戸建て5棟、マンション10室相当の不動産を所有することで達成できます。
業務的規模になることで、青色申告特別控除や専従者控除など、さまざまな節税の特典が受けられる一方、所得が増えることによる増税や、本業において服務規程違反となる可能性もあります。
不動産投資を拡大する過程にも、良い点と注意すべき点があり、これらを正しく把握し、適切に対応することが大切です。